一関ベイシー九訪記
- 前代未聞の10連休は敬遠して、5月も下旬になったので、またぞろ東北の方へ濁り湯めぐりに行ったついでに、ベイシーに寄ってきました。今年の桜は、近場の一本桜である「外大野のしだれ桜」と、邦画で昔の小学校の場面が出てくれば殆どがココでのロケだと言う旧小学校跡のキレイな桜くらいで済ませていたんで、遠出は久しぶりでした。快晴の中を走る高速は気分が良く、一気に秋田港に着いてしまいました。話に聞いていたけど、まだ登ったことが無かった100米もの高みにある展望塔から見た、好天の日本海は絶景でした。ここから出る苫小牧行きのフェリーの埠頭も見えました。
- そのまま八郎潟の方に向かって、初日の濁り湯は「湯の腰温泉」にしました。翌朝の「松川温泉」が何とも良いお湯で、気持ち良くなったのでそのまま「ベイシー」に一走り。まぁ、週末だから体調でも崩していない限りは、「随時定休日」じゃないだろうとの読みが当たり、2時に着いたら店頭のランプが付いていたので一安心。(これまでも何度か、「随時定休日」では、ほぞを噛んだ覚えがあるのです。)
- ベイシーを出て盛岡に戻ると、田沢湖の水沢温泉郷の「元湯」を楽しんで2日目は終わり。3日目は、朝風呂をやっている「子安峡」、10時から入れる「泥湯温泉」と巡って、栗駒に向かって「須川温泉」と「栗駒山荘」と7湯の濁り湯めぐりを満喫出来ました。Nelsonは老境に入って慢性の湿疹持ちなんですが、これだけの硫黄泉に連続して入った御蔭で、流石のしつこい患部の跡形もなくなりました。
- 娘がViberで「今日は、ベイシーはやってるのぉ・・・」と心配してくれましたが、店頭の駐車場に他県ナンバーが停まっているので安心と見て、いつもの市営駐車場に車を置いて入店。さっと目を走らせるとシェリー・マンのジャケットが掛かっていて、スイフティーよりもカッチリ目の、軽快なドラムスが店内に満ちていました。客の入りは、まぁ、10人くらいですから、普通の賑わいですね。
今日のセット・リスト
- 一人聴きなんで、いつもの正面壁際に座りました。
- 「Shelly Manne and His Men at the Blackhawk Vol 1」
入り口を入ると直ぐに、何だか爽やかで快調な音が聞こえてきたので、椅子に座ってサッと右側のレジ横のジャケ置き場を見ると、右掲盤がかかっていました。西海岸らしい乾いた音をシュアのV-15IIIが、いつも通りにキッチリと聴かせています。コーヒーを頼んでから店内を眺め渡すと、特に変わりはないようで、菅原さんがハナ眼鏡で原稿をチェックしているのが見える。そう言えば前を通ったレジには、書籍が平積みされた山が二つありました。左を見ると、久光さん由来のレコード棚のガラス戸に、この先達の伝記らしき本のポスターが貼ってある。
- 「At Music inn with Sonny Rollins」
御贔屓のロリンズだけど、我が家ではあまりかけないライブ盤です。先週のスパイスの項で話題にした「What's My Name/ Sonny Rollins」と同じMetro Jazzレーベルの盤で、こっちは東海岸にあるJohn Lewisが校長をしていた音楽学校でのライブです。絶好調期のライブらしさが横溢したテナーから出る音の豪快さと、節回しの見事さは、彼ならではのモノです。ふと天井に目をやると、前からそうだったかどうか、記憶が定かではないのですが、2階の床板を一部外して吹き抜けになっていて、音がイケイケになっているのに気付きました。1階だって聴き部屋だけでなく、それと同じ大きさの機器置き場、キッチン、応接セットがある部屋が横にあります。これに加えて、その上の2階も含めた空間があってこそ、100dBという高能率を誇る130Aのプロ版である、2220Bの2発入り密閉箱2機が気持ち良さげに鳴るのだなぁ・・・と今更ながらに納得しました。
 「A Night at Birdland with the Art Blakey Quintet Vol 2」 「A Night at Birdland with the Art Blakey Quintet Vol 2」
NelsonのBN入門盤だったこの2枚組盤の、「Wee-Dot」で始まって、「Quicksilver」で御大の前説が聴けるから、2枚目のいわゆる 「青盤」です。この店で青盤を聴くのは初めてのことです。この2枚目では、座付き司会者のPee-Wee Marquetteのあおり、というのか司会も楽しめます。お二人の語りなんかは眼前でマイクにカブリ付いている様子が彷彿とするリアルさがありますが、人気盤で絶えずかけるからでしょうか、ブラウニーやルーのフル・トーンがクリップ直前になると、割れそうになるのは致し方ありません。むしろ、ダイアモンド針でビニールの溝を引っ掻くだけでここまでの迫真の音が出せると言う、アナログ録音技術と、菅原さん入魂のシステム構築及び維持の努力に黙って脱帽する見識を、我々聴く側も持たねばならないと思います。そこだけを採り上げれば、まぁ、今ではCDで聴くのが吉かも知れませんが・・・ 「青盤」です。この店で青盤を聴くのは初めてのことです。この2枚目では、座付き司会者のPee-Wee Marquetteのあおり、というのか司会も楽しめます。お二人の語りなんかは眼前でマイクにカブリ付いている様子が彷彿とするリアルさがありますが、人気盤で絶えずかけるからでしょうか、ブラウニーやルーのフル・トーンがクリップ直前になると、割れそうになるのは致し方ありません。むしろ、ダイアモンド針でビニールの溝を引っ掻くだけでここまでの迫真の音が出せると言う、アナログ録音技術と、菅原さん入魂のシステム構築及び維持の努力に黙って脱帽する見識を、我々聴く側も持たねばならないと思います。そこだけを採り上げれば、まぁ、今ではCDで聴くのが吉かも知れませんが・・・
- 「In Person, Saturday Night at the Blackhawk/ Miles Davis」
これが掛かったのを潮時にして、お店を出ました。
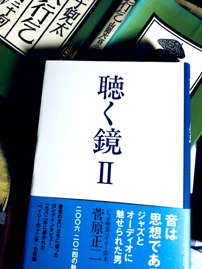
- レジに行って支払いをした時に、さっき目に付いた平積み本が「聴く鏡」の続編だと判りました。我が国では定価販売と言う商慣行がまだ残っていて、どこで買っても同じなんで、「コレ、貰います。」と声を掛けました。そうしたら、レジ嬢が「今、菅原さんが居ますから、サイン出来ますけど・・・」と誘われたので、サインを貰って二言、三言声を交わしました。
- 菅原さんと言葉を交わしたのは、久しぶりでした。大昔、今から30年も前の、まだ「ベイシーではリクェストは無し」だと言う慣行を知らなかった頃のことです。店内がNelson一人だったんで、このシステムで鳴らすと板橋盤はどんな音がするのかと思って、レジに行きました。コレもただ一人で店を回していた菅原さんに、「板さんの「濤」がもしあったら、掛けてくれませんか。」と頼んだら、素気無く「無いっ」と断られました。
- それ位の事でへこたれるNelsonではなく、表裏2曲しか入っていないので各楽器のアドリブが長く(内容も素晴らしいのですが)、音色が克明に把握できる盤として思い浮かんだので、「それじゃぁ、マックス・ローチの「Speak,Brother, Speak!」は?」と粘ったら、黙って頷いてくれました。
ドラムスがリーダーの盤だから機嫌が直ったのでしょうか・・・
既に用意していた「Lady in Satin/ Billie Holiday」盤の次に掛けて貰った・・・
その時以来のことでした。
|
 (Home - Jazz Audio 覚え書き / BACK)
(Home - Jazz Audio 覚え書き / BACK)