
- McCoy Tynerは、1937年にPhillyの西地区に生まれたピアニストで、「Art Farmer-Benny Golson Jazztet」(1960)への参加がジャズ界への初登場と思っていましたが、今回調べ直したらその前年に同じくBenny Golsonが彼を引き入れたと思える「Imagination/ Curtis Fuller 」盤(Savoy, 1959)が録音されています。両盤の録音日は2か月の差ですから、相前後して発売されたと思えます。Tynerは、同じPhilly仲間であるJohn Coltraneとは50年代末頃からの付き合いで、58年初にJohn Coltraneが録音した「The Believer」盤の標題となった曲は、マッコイが作った曲でした。後にJohn Coltraneカルテットにピアニストとして参加して、最初に発売されたのが、「My Favorite Things」でした。このバンドのベーシストで、5コ上のJimmy Garrisonは、彼ら二人の同郷の先輩でした。
- Coltraneカルテットに入ってからのマッコイのピアノの変化というか、発展と言うべきものは、Nelsonの不得手な楽理のこととなります。多分、四度和音とか、ペンタトニックとかいうキーワードに関わることと、誰にも判るリズムの細分化と多音の三連符とが絡まり合って独特の浮遊感と、カタルシスを伴う解決感なんかじゃないか、と個人的には捉えています。それが、その後のモダンジャズの大きな潮流になって行くのは、Coltraneが先導して、McCoyとElvinが脇を固めたいわゆる(クラシック・カルテット」の、65年頃までの活動がもたらしたものだと思います。
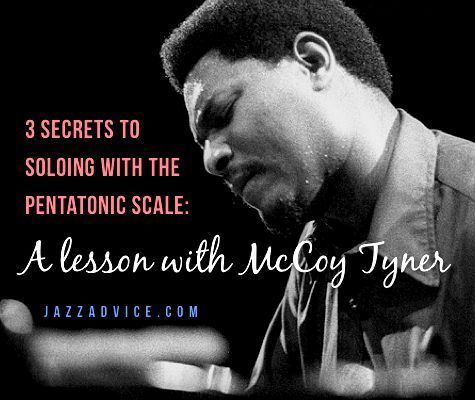
- もう一つ、触れておきたいことがあります。マイルスとの音楽感の違いですが、個人的にもまだ整理がついていないのに恐縮ですが、少しメモを試みます。マイルスは、コルトレーンの偉大さを認める発言を何度もしており、その時には彼のバンドでのマッコイの重要な役割を称賛していました。しかし、マッコイが自己のバンドを持つようになってからの演奏を、マイルスがあまり好まなかったこともまた、良く指摘されることです。生来の演奏スタイルからして、マイルスはチェット等と同様に、音を節約して必要不可欠な音しか吹かない方ですから、リズムの細分化に不可欠な、多音を駆使したガンガン弾きのマッコイを嫌ったのかも知れません。そして色んなジャズを聴いてくると感じることですが、この差異は楽器の演奏技術とも関係することでもあるようです・・・
- 馬鹿テクの人は一般的に、音符を大量に消費する傾向があります。普通の、あるいは時にたどたどしく聞こえる風なテクの持ち主の場合、アレヨ、アレヨと言う程には音数は使わずに演奏します。別の見方をすると、馬鹿テクの人は音、または楽器扱いに淫する傾向があり、「樹を見て森を見ず」気味に、大量の音を消費します。ですから、「そんなに沢山の音を使わなくても、アンタの言いたいことは言えるんじゃないの・・・」などと、からかう人が居るのです。
- 鳥獣戯画のように、余り沢山の筆数を要さずに、しかし人を感動させる表現の方法は、ジャズの場合にもあって、マイルスやチェットはその手のジャズメンです。猛烈な練習により馬鹿テクに近い域に達したコルトレーンに、マイルスがある時言ったことは別の所でも触れましたが、ここで繰り返します。マイルスは自分のソロを終えると舞台の袖に消えて、しばらく戻らないのが常でした。ある時、散々舞台裏で馬鹿話をしてからマイルスがやおら舞台に戻ると、コルトレーンがまだソロを終えていませんでした。「これは一言言って置くべきだナ。」と感じたマイルスは、ギグを終えた後にコルトレーンに「お前のソロは長すぎるゾ。」と指摘します。
- 自分でもその自覚があったコルトレーンは、「色々と枝分かれする展開の全てを、吹き尽くさないとサックスを置けないんです。」とマイルスに白状します。するとマイルスは呆れたようにただ一言、「そんなの・・・サックスを口から外せば良いだけのことじゃないか。」とコルトレーンに告げたと言います。そこには、プロとしてのマイルスの冷静な思考が読み取れます。我を忘れて、妄我の心境で力一杯にソロをすることは必要であっても、演奏全体の構想を維持することの方がもっと大事だと、マイルスは考える人なのです。しかし、当時のコルトレーンは丸でド素人のように、眼の前の曲に淫して、森全体の輪郭が見えなくなっていたのでした。
以下に、87歳の2006年頃に受けたインタビューで、McCoyが話したことを紹介しますが、それは次回の(2)になります。
(Home - 「ご当地ジャズメン列伝」 /「Philadelphia」 / BACK)

|


 (Home - 「ご当地ジャズメン列伝」 /「Philadelphia」 / BACK)
(Home - 「ご当地ジャズメン列伝」 /「Philadelphia」 / BACK)
